■#002│野逸バーガー

ウィーン
ハンバーガーショップの自動ドアが滑るように開くと、フライドポテトの香りが一行の鼻孔をくすぐった。
「うわぁ、なんだかおいしそうなニオイ…」
「いらっしゃいませ、『キング・スクランブル』へようこそ。お持ち帰りでしょうか? それともこちらで召し上がって行かれますか?」

ももたろう一行が入店すると、店長とおぼしき男性が声をかけてきた。
「わたし、こういうお店初めてで…何がおススメですか?」
「はい、当店のオススメは、何と言っても野逸港のご当地バーガーである『まぐろメンチバーガー』です。パテは牛肉ではなく、野逸港で水揚げされたビンチョウマグロのメンチカツを使っています」
「まあ、それは美味しそうですこと」
閼伽凛皇女が興味を示すと、キジの女の子が補足した。
「自分は地元なんで、このお店には何度も来たことありやす。『まぐろメンチバーガー』は厚めのカツに特製タルタルソースがかかっていて、ボリュームの割にヘルシーだと評判なんスよ!」
「え~!んじゃわたしそれにする~」
「いくつ食べるでありやすか?」
「んー、今なら3つはイケるかも!」
「わたくしも…」
「あたしなんて4つはイケちゃうよ!」
一行は会計を済ませると、中庭のテラス席に陣取った。程なくして女性の店員が料理をワゴンに載せて運んできた。

「お待たせしましたー。『まぐろメンチバーガー』のドリンクセットです」
「いやーん!美味しそうな匂い。さっそくいただきましょう」
「どうぞ召し上がれ。ところでお客さんたちの中に、最近『激レアな体験』をした人はいませんか?」
「え? 『激レアな体験』ですか?」
「んー、みんななんかある?」
「いいえ、特にそういうことはないですわね」
「自分も特にないでありやす」
「あたしも思いつかないなぁ」
「そうですか、残念。そういえば皆さんもFBCを見にいらしたの?」
「FBC? それは何ですの?」
「あら、違ったようね、ごめんなさい。FBCというのは“フードバトルチャンピオンシップ”の略で、要するに大喰い大会なんだけど、ちょうどこの後、野逸コロシアムで全国大会が開催されるの」
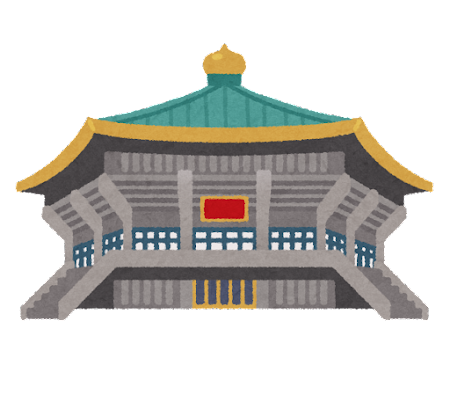
「へーそうだったんだ。どうりで観光客が多いと思ったわ」
「面白そうね。ちょっと観戦したい気もするなぁ」
「もし良かったら私と一緒に見に行きませんか? ファミリーチケットがあって、あと4人まで一緒に入場できるのよ。本当は孤児院で一緒に育った子を誘ったんだけど、都合が悪いらしいの」
「どうもありがとう。是非ご一緒させていただくわ」
「良かった。私はあと一時間くらいで上がりだから、この席で待っていてくださいな」
「はーい、じゃあよろしくお願いいたします」
「さーて、んじゃお腹も空いたし、いただきましょう」
「いただくでありやーす!」
全員がバーガーに手を伸ばそうとした次の瞬間、テーブルの上を大きな『塊』が通過した。
みながぎょっとして手を止めたが、我に返った時にはテーブルの上にあったはずの『まぐろメンチバーガー』はすべて忽然と姿を消していた。
そう、先ほどの『塊』によってバーガーは根こそぎかっさらわれてしまっていたのだ。
「きゃぁ! バーガー無くなってるし!」
「『し』叱らないでー」
声がした方を見上げると、木の枝にサルの女の子が座っていた。肩に大きな袋を担いでいる。
その袋の中に『まぐろメンチバーガー』が入っているようだ。つまり『まぐろメンチバーガー』が盗まれたことは明らかだった。
これにはイヌの少女も怒り心頭し、歯ぎしりしながらサルの女の子を睨みつけた。
「れにちゃん、顔が怖いよ、かお!」
「『お』怒らないでー」
騒ぎを聞きつけて先ほどの女性店員が戻ってきた。
「こらー! 詩織、あんたお客様になんてことするのよ! いったいどういうつもり!?」
「『り』リズムにのってー」
「うぬーッ!絶対に許さーん!」
「『ん』んー…今日も一緒にー、レッツ、オラキオのカッパ館!」
『まぐろメンチバーガー』という戦利品をたっぷりせしめると、サルの女の子は意味不明な掛け声を残して、上機嫌で裏山の方へ消えていった。
すると女性店員が平身低頭、恐縮しきって頭をさげた。
「みなさん、本当にごめんなさい。すぐに作りなおしますのでお時間くださる?」
「店員さんはあのおサルさんのこと、ご存知なのですか?」
「はい。あの子は詩織といって、私と同じ孤児院で育ったんです。本当は泣き虫で甘えん坊な子なんですが、このところいたずらが過ぎてしまって、あまりにも皆が手を焼くので町の人からは『若大将』なんて呼ばれています」
「女の子なのに『若大将』って」
「ひょっとして、FBCに誘ったというのはあの子のことかしら?」
「ええ。でも今日は大事な用があるとかで…」

